北辰テストも
適切な問題集で取り組めば
必ず得点をアップできます。
「定期テストで得点できていても
北辰テストでは、なかなか得点できない…」
という生徒たちはたくさんいます。
北辰テストは、ほぼ入試と同じような問題のため、
北辰テスト対策=入試対策といった感じになり、
英語、数学、国語については、
定期テストの勉強法では通用しないのが実情です。
ただ、北辰テストも入試も
出題される問題は決まっているので
適切な問題集でステップを踏んで取り組むことで
だれでも得点をアップさせることは可能です。
塾の生徒たちも
北辰テスト対策の勉強に取り組んだ科目については、
ほぼ確実に得点をアップできています。
中には20点、30点以上アップする生徒もいます。
ここでは、北辰テストをアップさせるために必要な
科目別のテキストと取り組み方について紹介していきます。
詳細については、随時アップしていく予定ですが、
早めに知りたい方は直接電話、又はメールにてお問い合わせください。
セルフレクチャー
⇒声に出して自分に問題の解き方や答えの根拠を説明すること
北辰の得点アップに効果のある
オススメの問題集と取り組み方

国語
『北辰のかこもん』
『埼玉県公立高校6年間入試と研究』(声の教育社)

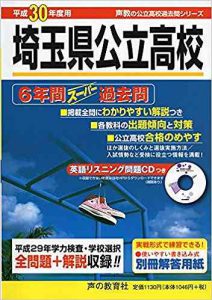
自分にスラスラ授業ができるようになるまで繰り返そう
ステップ1
答えと必要な解説を赤ペンで記入する
問題は自力で解いても、
解かずに答えを赤で記入しても
どちらでもOKです。
北辰テストで70点以上取れていない段階で
自力で解いても力はつきづらいため、
テスト結果が70点以下の人は、
まずは説明できる問題の数が少なくとも10回分、
できれば20回分にはやくなるよう
最初の20回分までは、自力で解かず
先に赤ペンで答えを書いて学習を進めた方が
力がつき、テスト結果はアップしやすいです。
赤で答えを記入したあと、
問題文と解説を読み、
問題文の解答根拠のところに蛍光ペンをつけます。
また、その問題の解き方の説明を自分でできるように
必要な解説を問題用紙に赤で書き込みます。
解説を読む際は
「ふむふむ、なるほど、
こんな流れで正解を見つけていけばいいのか…」
といった気楽な感じで読んでいけばOKです。
選択肢の問題は、
間違っている箇所に『×』を書き込みましょう。
解説を読んでも
「なぜその答えになるのかわからない問題」については
【☆】印をつけ、先生や塾の先生に確認しましょう。
ステップ2
セルフレクチャーを行う
必要な解説などを記入が終わったら
自分自身に説明(授業)をする感じで、
一問一問セルフレクチャーをやってみましょう。
セルフレクチャーの回数は5~7回ぐらいやりましょう。
国語は、セルフレクチャーを行うことでかなり力がつきます。
人にもよるのですが、
だいたい5回分ぐらいをやると
得点がアップする生徒たちが多く、
15~20回分ぐらいやることで、
本文の読み方のコツと問題の解き方のコツがつかめ、
得点が安定してきます。
『北辰のかこもん』は問題が7回分しかないのですが、
公立入試の過去問
『埼玉県公立高校6年間入試と研究』
をやることで合計13回分の
セルフレクチャーに取り組むことができます。
国語が苦手な生徒は、
A3に拡大コピーして取り組むといいです。

国語で力がつきにくい勉強法は
新しい問題をどんどん解きまくり
復習しないというやり方です。
「国語の点数が上がらない」
と塾に来てくれた生徒たちは、
かなりの数の問題を解いている
(多い生徒の場合は、100題以上)のですが、
新しい問題をどんどん解きまくり
復習やセルフレクチャーをしていないので
ほとんど力がついていないという場合をよく見かけます。
本文の読み方のコツ
国語は、小説と説明文があるのですが、
読み方のコツとしては、
小説は、登場人物のキャラクターと情景をイメージしながら
説明文は、【作者がイイタイコト】ってざっくり何なんだろう?と
 意識しながら読むといいです。
意識しながら読むといいです。
説明文については、偏差値60以上の高校を受験する場合は、
できれば重要箇所のマーキングの仕方を覚えておくと
得点が安定するのでオススメです。
説明文の重要箇所のマーキングの仕方は
近日中にアップします。
文法問題対策
文法問題は、配点が少ないので苦手な人は捨ててOKです。
やっておきたい人は、
『高校入試合格へのベストアプローチ国文法』
がもっともわかりやすく文法について解説してあります。

これを読みながら、
『定期テスト基礎からぐんぐん中学国語文法・古典』
と『北辰のかこもん』をやっておけば
文法問題で落とすことはなくなります。
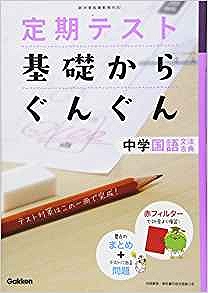
どちらもすごくわかりやすいので、
定期テストの文法問題対策の参考書と問題集として
持っておくのもオススメです。
漢字、4字熟語、慣用句対策
北辰、公立入試の漢字、4字熟語、慣用句対策としては
『システム中学国語 漢字・語彙編』
が最もおススメです。

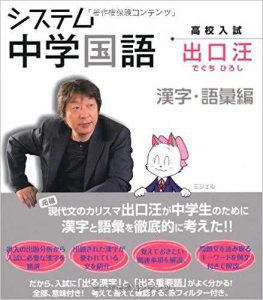
これ1冊やっておけば、
あとは、毎回の定期テストで
試験範囲の漢字を覚えていくだけで、
この分野は大丈夫です。
数学
『北辰のかこもん』
『やさしい中学数学』
『とってもやさしい数学』
北辰テスト特有の問題の解き方のマスターしよう
ステップ1
答えと必要な解説を赤ペンで記入する
『北辰のかこもん』に
先に答えと必要な解説や途中式を赤ペンで書き込み
どの問題も見た瞬間、解き方がわかるように
繰り返しセルフレクチャーを行いましょう。

計算問題は自力で解いても大丈夫ですが、
間違った問題については、
復習のとき自分がわかりやすいように
赤ペンで解き方のポイントと流れを書きましょう。
解き方がわからない、
忘れてしまっている分野などについては、
『とってもやさしい数学』と『やさしい中学数学』
の2冊を使って復習しながら、
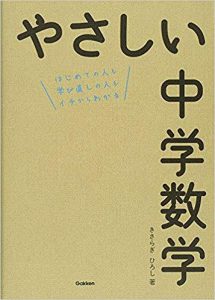
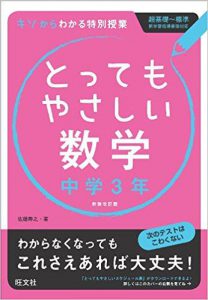
『北辰のかこもん』のできる問題集を増やすことを中心に
学習を進めていきましょう。
北辰テストは、かなり難しい問題が20~30点分ぐらいあるので、
まずは、大問1の50点分をしっかり取り組み、
大問2,3,4はできる問題を習得していく感じがいいでしょう。
ステップ2
セルフレクチャで解き方の理解を深める
(解き方のわかる問題数を増やす)
『北辰のかこもん』に赤ペンで記入した解き方を
繰り返し読んで復習します。

復習のときは、
実際に問題を解くと時間がかかりすぎ、
他の科目の勉強時間ができなくなるため、
【解き方の流れを声に出して説明していく】
セルフレクチャーでやっていきましょう。
どの問題も同じような問題が出たら
すぐに解けるようになることが大切です。
解説を読んでも理解できない問題については、
学校や塾の先生に聞きましょう。
解説を読んだり、先生に聞いたりしても
理解できそうもない問題4~10題は捨てても大丈夫です。
4題捨てても80点とれるので偏差値65-70近くにはなります。
北辰や入試の数学は
先生たちでも時間内に解けないような難問が
2~4題ぐらいあることもあります。
これらの問題に時間を使うのはもったいないので、
難問は捨てて、
できるだけ確実にできる問題の数を増やすことが大切です。
ステップ3
実際に解いてみる
問題を見た瞬間解けると思ったら、
(◎が2つの問題数が増えたら)
実際に解いてみます。
間違った問題には△をつけ、解きなおします。
北辰の数学は数字がかわるだけで
毎年似たような問題が出題されることがよくあるので
過去問を3年分ぐらいやると
かなり得点をアップできるようになります。
数学を得点源にしたい人
数学をある程度得点源にしたい人は、
北辰や入試特有の問題の解き方をマスターする必要があるので、
『やさしい中学数学』を読み、
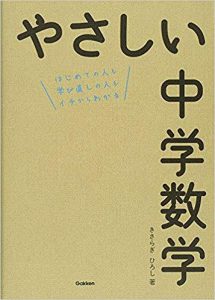
この問題集に出ている
すべての問題を解き方を読みながら理解していきましょう。
また、12月からできるだけ多くの
埼玉県の公立入試の過去問の問題の解き方を覚えつつ、
平行して
『中学数学発展篇 入試実践』の解き方を覚えていくといいです。
数学が苦手な人
数学が苦手な生徒は、A3に拡大コピーして取り組むといいです。
また、
『とってもやさしい数学』と
『やさしい中学数学』で
『北辰のかこもん』を解くために必要なところを読み、
まずは過去問を1問でも多く解けるようにしましょう。
英語
英文法
『ホントにわかる英語』
『とってもすっきり英語』(偏差値45以上の高校受験者)
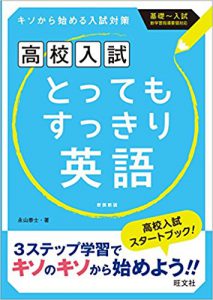
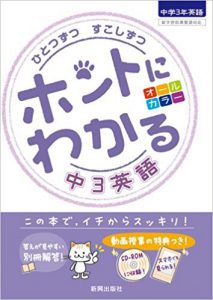
英語長文
『教科書ガイド』(偏差値40ぐらいの高校受験者)
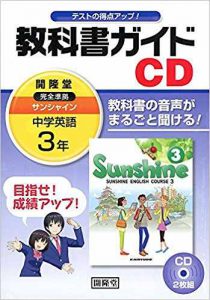
『中学英語レベル別問題集1』北辰入門レベル(春休み~夏休み)
『ハイパー英語教室中学英語長文 1』北辰基礎レベル(春休み~夏休み)
『中学英語レベル別問題集2』北辰・公立入試レベル(夏休み)
『ハイパー英語教室中学英語長文 2』公立入試レベル(夏休み~冬休み)
英語については、
あまり『北辰のかこもん』は有効ではありません。
やりたい人は参考程度にやってもいいのですが、
得点アップしたい人は
英文法の基礎学習と
英文の音読(CDを利用した黙読でもOK)に取り組みましょう。
CDを利用した音読は特にオススメです。
音読に取り組んだ生徒たちは、
ほぼ全員が北辰や入試で英語の得点を大きくアップさせています。
英語の北辰テストは、
7月ぐらいから難しくなるため、
英文法の基礎と長文の音読をやっておかないと
7月以降はなかなか得点できなくなります。
英文法対策
英文法については、
『ホントにわかる英語』
が一番わかりやすくておススメです。
すべての中学生はまずは
これを繰り返し読み
英文法の基本をマスターしましょう。
偏差値45以上の高校を受験する人は、
『とってもすっきり英語』
まで取り組んでおくと、
北辰テストや入試で
文法問題でわからない問題がなくなるので
できれば取り組むことをおススメします。
偏差値55以上の高校を受験する人は
必ず取り組みましょう。
文法については、北辰や公立入試では
これ以上必要ないので、
あとは配点の高い
長文読解とリスニング対策に取り組みましょう。
英語長文対策
英語長文の問題は、
読めてしまえば、小学生5年生ぐらいの話の内容なので
簡単に問題は解けるのですが、
北辰や入試の文章は、
学校の定期テストに比べると英文の量が多いため、
学校の習うような感じで、
英文を一文づつを後戻りしながら日本語訳していると
時間が足りなくなってしまいます。
英文を速く正確に読めるようになるためには、
カタマリごとの意味を把握しながら、
英文を頭から順番に読んで理解できるようになることが必要です。
英文を頭から順番に読んで理解できるようになるには
英文の音読が最も効果的で、
塾の生徒たちでも音読に取り組んだ生徒たちは、
北辰や入試で英語の得点を大きくアップさせています。
実際に音読するテキストとしては、
①『教科書ガイド』(偏差値40ぐらいのまでの高校受験者)
②『中学英語レベル別問題集1』北辰入門レベル(春休み~夏休み)5文
③『ハイパー英語教室中学英語長文 1』北辰基礎レベル(春休み~夏休み)20文
④『中学英語レベル別問題集2』北辰・公立入試レベル(夏休み)5文
⑤『ハイパー英語教室中学英語長文 2』公立入試レベル(夏休み~冬休み)20文
⑥『中学英語レベル別問題集3』北辰・公立入試レベル(冬休み)5文
に取り組んでいくといいでしょう。
『中学英語レベル別問題集』1~3は
文法問題は飛ばして、英語の長文問題を解かず
長文問題の音読だけ行えばOKです。
②~⑥のすべての問題集には、CDがついています。
音読するテキストのおおまかな目安としては、
偏差値40ぐらいまでの高校を受験 ①のみ
偏差値41-45ぐらいの高校を受験 ②まで
偏差値46-50ぐらいの高校を受験 ③まで
偏差値51-55ぐらいの高校を受験 ④まで
偏差値56-60ぐらいの高校を受験 ⑤まで
偏差値61-70ぐらいの高校を受験 ⑥まで
音読を行うときの注意点
音読を行うときの注意点は
①できるだけCDの真似をして読む
(リスニングがはっきり聞こえるようになります。)
②単語ひとつひとつの意味がわかりながら読む
③主語と動詞を把握して読む
の3つです。
理科と社会について
理科と社会については、
定期テスト対策でも使用する
下記のテキストが北辰や入試対策には最適です。
特に『くもんの基礎がため100%』に取り組むと
理社の北辰の得点を大きくアップする生徒たちが多いです。
※『くもんの基礎がため100%』に取り組むには、
その前に『ひとつひとつ』や『とってもやさしい』に
取り組んでおく必要があります。
どの問題集も自力で解く必要はなく、
赤で答えと自分にとって必要な解説を書き込み
どの問題も見た瞬間に答えや解き方がわかるようになれるよう
できるだけ繰り返し読みましょう。
ある程度覚えられたら赤シートでチェックテストをしましょう。
理科
偏差値45ぐらいのまでの高校受験者
①『とってもやさしい理科』
②『北辰のかこもん』
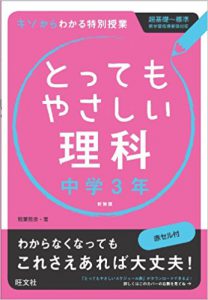

偏差値45ぐらいのまでの高校を受験予定の人は、
この2冊でを繰り返すことで偏差値45-50ぐらいまで取れます。
『北辰のかこもん』は、50-70点分の問題に取り組み、
難しいと感じる30~50%ぐらいの問題はやらなくても大丈夫です。
③『必勝埼玉 理科』(※塾用問題集)

埼玉県の入試でよく出題される問題を集めた問題集で、
北辰にも同じような問題がよく出題されるので、
できれば偏差値45ぐらいのまでの高校を受験予定の人も
これの一問一答だけでもやっておくと10点ぐらい得点がアップできます。
手に入るようであればぜひ取り組みましょう。
偏差値45-55の高校受験者
④『くもんの基礎がため100%』
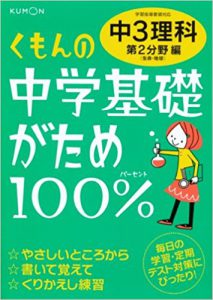
偏差値45ぐらいのまでの高校を受験予定の人は、
①⇒④⇒②⇒③の順番で、単元別に読んでいきましょう。
単元別とは、①で天気を読んだら
④、②、③で天気のとろこを引き続き読んでいく感じです。
3つの中でも、できるだけ④を繰り返し読み、
同じような問題が出題されたら解けるようにしておくて
北辰、入試で理科を得意科目にできます。
④をしっかり取り組んだ多くの生徒たちが、
理科の得点を大きくアップさせています。
偏差値55以上の高校受験者
⑤『中学総合的研究問題集 』

①~④までが終わった後に取り組む問題集で、
偏差値55以上の高校を受験予定の人は、
理科の点数を高得点で安定させるために
できれば取り組んでおいたほうがいいです。
問題は、北辰や入試によく出る問題を分野別に集めたもので
④がスラスラできるようになってないとすこし辛いです。
ちょっと理解しずらい問題などは、
⑥を読むと理解できることが多いので、
⑥を持っておくと便利です。
偏差値60以上の高校受験者
⑥『図でわかる中学理科』


北辰や入試に出題される標準問題のみを扱った問題集で、
偏差値60以上の高校を受験する人は
やっておくと理科を得意科目にできます。
解説は非常に詳しいので、
読むだけでも力がつきやすく、
わからない問題があったときに調べたりするのにも使えます。
数学や国語と違い、『北辰のかこもん』だけで
得点アップするのは難しいため
①から順番に取り組んでいきましょう。
iワークや、keyワーク、シリウス、必修テキストなどの塾用問題集は、
問題量が多すぎて
理科で毎回90点以上とるような生徒たちでも
定着できないまま入試を迎えてしまうためオススメしません。
社会
①『ひとつひとつわかりやすく』偏差値40ぐらいのまでの高校受験者
②『とってもやさしい』偏差値40ぐらいのまでの高校受験者
③『北辰のかこもん』
④『中学歴史が面白いほどわかる本』偏差値50以上の高校受験者
⑤『くもんの基礎がため100%』(公民は政治編のみ。地理と歴史のみでも可。)
⑥『必勝埼玉 社会』(※塾用問題集)
⑦『中学総合的研究問題集 』 偏差値55以上の高校受験者