
問題が解けるようになる【問題集の取り組み方】
ここからは具体的に
問題が解けるようになるための【問題集の取り組み方】を
説明していきたいと思います。
大まかな問題集の取り組み方は次のような流れです。


英語、国語、理科、社会は
大まかにこの流れで取り組むといいです。
数学については、計算問題と関数・図形などで
取り組み方が違うので、
こちらを参考にしてください。
ステップ1 答えを【赤ペン】で記入

まずは問題集に
【赤ペン】で解答を見ながら
問題の答えを記入していきます。
この時、問題を読みながらやっても、
 読まずにただ書き写しても
読まずにただ書き写しても
どちらでもOKです。
答えを【赤ペン】で書いているうちに、
テストに出るポイントが自然とわかってきます。
ステップ2 問題と答えと解説を読む(3~5回)

記入が終えたら、
次に、【赤ペン】で記入した問題集の
問題⇨解説⇨解答
と、【なぜその答えになるのかをきちんと理解すること】
に重点をおき読んでいきましょう。
解説を読み、
【なぜその答えになるのかを理解すること】
はとても大切です。
ざっと3~5回ぐらい読みましょう。
試験には、問題集とほとんど同じような問題が出ます。
1〜2周目までは、
きちんと理解する必要があるため
時間もかかり大変なのですが、
3周目からは半分以下の時間で
スラスラ進めることができます。
4〜6周ぐらいざっと繰り返すと、
ほとんどの問題が
見た瞬間に答えや解き方がわかるようになってきます。
見た瞬間に答えや解き方がわかる問題が
増えれば増えるほど
テストの得点はアップします。
最初の1〜2周を乗り越え
問題を見た瞬間に
答えや解き方がわかるようになるまで
できるだけ繰り返し読みましょう。
|
解説を読むと理解が深まり また繰り返し読んでいるうちに また繰り返したことは
|

ステップ2での注意事項
※1 問題は答えだけでなく、必ず解説も読み、
大切だと思うところには
蛍光ペンでラインを引くようにしましょう
※2 解説を読んでも
【なぜその答えになるのよくわからない問題】
【よく理解できない問題】
に⭐️印をつけ、
付箋を貼って
学校や塾の先生やわかりそうな友人や家族などに
なぜその答えになるのかを
確認し理解するようにしましょう。
※3 数学や理科の計算問題などは、
答えだけでなく必ず式も書いておきましょう。
ステップ3 赤シートでチェックテスト(2~3回)
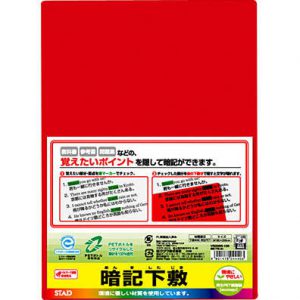
7~8割ぐらい覚えたかなと思ったら、
赤シートでチェックテストをしていきましょう。
間違った問題には、必ず『正』の字をつけ、
チェックテストの度にすぐに見直して覚えなおしてから、
次のチェックテストを行います。
「赤シートでチェックテストは面倒‥」
「赤シートだと書いた答えがうっすら見えてやりにくい」
という人は、
もう一冊同じ問題集を用意して、
そちらでテストするのもオススメです。

2冊同じ問題集を買ってやっている生徒たちも結構います。
自分も受験の時は、そうしました。
チェックテストを2〜3回やっているうちに、
試験に出る問題とその答えを
いつの間にかほとんど覚えられてしまいます。
ステップ4 間違った問題の覚え直し

チェックテストで、『正』の字がついた問題を
もう一度全部覚え直してから、
最後のチェックテストに取り組みましょう。
全問正解できたらその問題集は終了です。

流れの中でも言ったのですが、
問題集の取り組み方の
最も大切な2つのポイントを
もう一度確認しておきましょう。
ポイント1
解説と答えを読んでも、
『なぜその答えになるのか』
よく理解できない問題には⭐️印をつけ、
必ず塾や先生に確認して
理解するようにしましょう。
ポイント2
どの問題も、
問題を見た瞬間に答えがわかるまで
繰り返し読みましょう。
