
数学の苦手な人の共通点をまとめて見ました。
数学の問題集の具体的な取り組み方については、
問題集の取り組み方(数学編)>を読んでください。
数学が苦手な人の共通点と解決策
その1:基礎ができていない
(難しい問題集をやっている)
【何をやっていいのかわからず勉強していない】
又は、
【基礎ができていないのに
難しい問題集を時間をかけて取り組み、
ほとんど力がついていない】
といったケースを本当によく見かけます。
このパターンは特に通っている塾で
難しい問題集
(新中問題集、keyワーク、フォレスタ、
iワーク、シリウス、必修テキストなど)
にいきなり取り組んでいる、
または進研ゼミに取り組んでいる生徒によく見られます。
|
進研ゼミはイラストなども多く、 偏差値65ぐらいの生徒や、 |
数学は基礎力が特に大切な科目なので、
まずは簡単な問題をスラスラ解けるようになってから
標準問題などに取り組まないと
時間がかかるわりに、
あまり学習した内容が身につきません。

解決策
➡︎『とってもやさしい数学』
→『数学の要点』又は
『くもんの基礎がため100%』と
やさしい問題からステップを踏んで学習を進め、
まずは基礎をしっかり固めましょう。
やさしい問題から取り組んだ方が、
勉強もサクサク進み、
基礎力も自然と着実についていきます。
また、これらの問題集で、
これまでに学習した中の
苦手な分野を克服していきましょう。
『とってもやさしい数学』だけだと、
問題量が少なく、
本当に基本的な内容の確認しかできません。
『数学の要点』又は
『くもんの基礎がため100%』まで取り組むと、
基礎力ができ苦手意識がなくなる生徒たちが多いです。
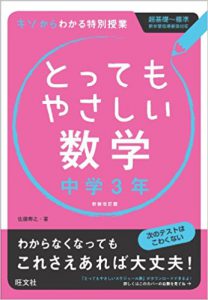 →
→  又は
又は 
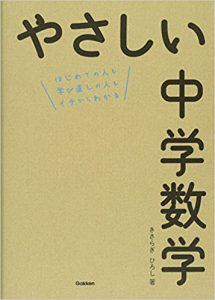
※『くもんの基礎がため100%』には、
問題の詳しい解説のあるのですが、
問題の例題のようなものがないため、
問題の解き方がわからない時などは、
『やさしい中学数学』
を読んで確認した方が
スムーズに学習を進められます。
その2:問題の演習量が少ない
数学は運動や楽器の練習と同じで、
その分野を理解を定着するためには、
ある程度の問題量をトレーニングする必要があります。

解決策
➡︎問題演習するための問題集は、
これまでの経験から
書き込みができる問題集がオススメです。
苦手分野の克服だけでよければ、
一番オススメなのは『数学の要点』で、
問題の量も苦手克服には十分です。
定期テストで80点以上目指す場合は、
『くもんの基礎がため100%』や
『iワーク』ぐらいの問題数をこなす必要があります。
その3:繰り返しが足りない
計算問題はある程度の問題数をやっていくうちに
だんだんと計算の流れに慣れ解けるようになってくるのですが、
計算問題以外の問題
(文章問題、関数、図形、確率、データの整理など)は、
1、2回解いただけで、できるようになれるのは
学年でトップクラスのかなり数学が得意な生徒だけです。
テストでは1、2回解いただけでは、
できない問題の方が多いため
かなり厳しい結果になってしまいます。

解決策
➡︎普通は4〜7回ぐらい繰り返すことで、
できるようになります。
毎回解いていると時間がかかってしまい
他の教科の勉強ができなくなる場合もあるので、
最初の3〜5回までは自力で解かずに、
問題と解説を繰り返し読み、
見た瞬間に解き方がわかるようになったと思ったら
本当にできるか実際に解いてみるといった方法がオススメです。
その4:途中式を飛ばす
途中式を面倒で飛ばしてしまい、
飛ばしたところで間違っていることがとても多いです。

解決策
➡︎途中式はひとつひとつきちんと書くように心がけましょう。
その方が結局は正確に早く計算できます。
その5:図を書かない(図が書けない)
苦手な生徒ほど図を書かずに解こうとして
わからなくなっていることが多いです。
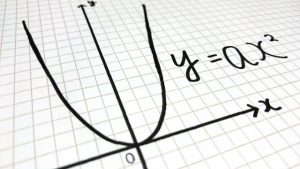
解決策
➡︎「図をどうやって書いたらいいのかわからない」
「どのような問題には図が必要なのかわからない」
といった生徒たちも多くいると思うので、
最初に解説などを読み、
まずは、どのような問題の場合には
図を書く必要があるかを知り、
どのように図を書いたらいいのかを
ひとつづつ学習していきましょう。
その6:計算式や文字などを小さく書く
理由はわからないのですが、
数学が苦手な生徒のほとんどが、
 計算式や文字などを小さく書くことが多いです。
計算式や文字などを小さく書くことが多いです。
計算式や文字が小さいため、
自分でも何をやっているのか
途中でわからなくなってしまっていたり、
どこで計算を間違ったのか
わからなくなっているケースを本当によく見かけます。

解決策
➡︎文字や計算式はできるだけ大きく書きましょう。
勉強の時は汚い字でも自分がわかりさえすれば大丈夫です。
文章問題や関数、図形などは
1題に1ページぐらい使った方が、
解き方の流れやどこで計算を間違えたのかなどが
よくわかりオススメです。